三笘薫選手のドリブルは、「楽しそうにディフェンダーを追い越して踊り、重要な場面で魔法をかけている。」
これは、英衛星放送「スカイ・スポーツ」のクリス・ボイド氏の記事からの引用です。
わかっているのに止められない。屈強なDFが次々と無力化されていく。
指導者の皆様や、お子様をサポートする保護者の皆様の中には、「あれは天性の才能だから」「ウチの子には真似できない」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、それは大きな誤解です。
様々なトップアスリートを分析してきた私の見解では、三笘選手の強さは「才能」という曖昧な言葉で片付けられるものではなく、「①科学的理論」「②理論を支える肉体」「③理論を再現する心理学」という、極めて緻密なシステムによって構築されています。
三苫選手は自身のプレーを「感覚」で終わらせず、筑波大学時代に「ドリブル」をテーマにした卒業論文で、そのメカニズムを科学的に解明しました。
この記事では、単なるスーパースターの紹介ではありません。
三苫選手が「なぜ抜けるのか」を解き明かした『卒論』という最強の理論、その理論をピッチで実行可能にした大学時代の『筋肉』という肉体改造、そして最高のパフォーマンスを常に再現するための『ルーティン』という心理的技術。
これら3つの要素を、ご提供いただいた資料と最新のスポーツ科学の知見から徹底的に解剖します。
三苫選手のことを調べれば調べるほど、あの”三苫の1mm”は、”偶然”ではく”必然”だったと思えます。
Japan’s second goal in their 2-1 win over Spain was checked by VAR to determine if the ball had gone out of play.
The video match officials used the goal line camera images to check if the ball was still partially on the line or not. pic.twitter.com/RhN8meei6Q
— FIFA (@FIFAcom) December 2, 2022
この記事を読み終える頃には、「才能がないから」という言葉が、選手の可能性を摘む言い訳に過ぎないことがお分かりいただけるはずです。
この記事でわかること
-
三笘選手の強さは「才能」ではなく、「理論」「肉体」「心理」の3要素で構築された科学的思考法にある。
-
筑波大学の卒業論文でドリブルを科学的に分析し、相手の重心や視線を読む「理論」を確立した。
-
大学4年間で計画的に肉体改造を行い、理論を実行可能にする強靭な「肉体」を作り上げた。
-
ルーティンやデータに基づく自己管理という「心理的技術」で、最高のパフォーマンスを安定して再現している。
目次
三苫薫とは?──天才ではなく、設計者としてのアスリート

多くの人が三笘選手を「天才ドリブラー」と呼びます。
しかし、そのキャリアを深く見ていくと、彼が天賦の才だけに頼ってきたわけではないことがわかります。むしろ彼は、自らのキャリアを冷静に分析し、長期的な視点で「設計」してきた、極めて知的なアスリートです。
まずは、三苫選手の基本的なプロフィールと、その思考の原点が垣間見えるキャリアの軌跡を見ていきましょう。
|
項目
|
詳細
|
|
生年月日
|
1997年5月20日
|
|
身長
|
178cm
|
|
体重
|
約73-74kg(プロ入り後)
|
|
出身
|
神奈川県川崎市
|
|
経歴
|
さぎぬまSC → 川崎フロンターレU-12/U-15/U-18 → 筑波大学 → 川崎フロンターレ → ユニオンSG(レンタル)→ ブライトン
|
特筆すべきは、体重の変遷です。高校時代には66kgに満たなかった体重を、大学4年間で72kgまで意図的に増量。さらにプレミアリーグという世界最高峰の舞台で戦うために、73-74kgまでビルドアップしています。
この数字の変化だけでも、彼がいかに計画的に肉体と向き合ってきたかが分かります。
異例のキャリア選択:18歳、プロへの道を断る決断
三苫選手のキャリアにおける最大の転換点は、高校卒業時に訪れます。
川崎フロンターレのトップチームからプロ契約の打診を受けたにもかかわらず、その道を一度断り、筑波大学への進学を選びました。
多くの有望な若手選手がプロの世界へ飛び込む中、これは極めて異例の決断でした。
その理由は、彼の冷静な自己分析能力にあります。「プロの世界で活躍できるという決定的な自信がなかった」「90分間を通して安定したパフォーマンスを発揮するためのフィジカルがまだ足りない」と、当時を振り返ります [7]。
これは、目先の成功に飛びつくのではなく、プロとして大成するために何が必要かを逆算し、4年間という時間を「戦略的投資」と位置づけたようです。
三苫選手は筑波大学という、スポーツ科学の最先端の研究環境を、自らを根本から作り変えるための「研究室」として選んだのです。この18歳での決断にこそ、彼のキャリア全体を貫く「思考するアスリート」としての原点を見ることができます。
【理論】なぜ三苫は抜けるのか?──卒業論文が解き明かしたドリブルの科学

三笘選手の代名詞であるドリブル。なぜ三苫選手のドリブルは、相手が対策を練っているとわかっていても止められないのでしょうか。その答えの核心は、筑波大学時代の卒業論文に隠されています。
三苫選手自身のプレーを「感覚」で終わらせず、科学のメスを入れて分析したのです。ただし、海外のインタビューで、”現在のプレーに論文はほとんど関係ない”と言っております。
論文が無意味、というわけではなく、大学時代の”現時点”を書いたのでしょう。時を経たら”進化する”のは当たり前。
それより、大学の卒業論文で、このような分析を行うほど、探究心と実行力がある証拠です。
卒業論文の衝撃:「ドリブルの学位を持つ男」の探求
三苫選手の卒業論文のテーマは「サッカーの1対1場面における攻撃側の情報処理に関する研究」。その目的は、熟練したドリブラーが、そうでない選手と比べて何を「見て」、どのように「情報処理」しているのかを科学的に解明することでした。
多くの学生アスリートが比較的取り組みやすい試合分析をテーマに選ぶ中、三笘選手は自ら仮説を立て、実験によって検証するという、極めて困難な道を選びました。
指導教官であった小井土正亮監督も、これは「極めて稀なケース」だったと語っています。彼はチームメイトの頭に小型カメラ『GoPro』を装着して視線の動きを記録し、「熟練者」と「非熟練者」の視覚パターンを比較するという、独創的な研究を行ったのです。
研究から導き出された「抜ける」ための3つの科学的根拠
この研究を通じて、三苫選手はドリブル突破のメカニズムを支える、いくつかの重要な科学的根拠を発見しました。
1.視線の使い方:ボールではなく、相手とスペースを見る 熟練した選手は、ドリブル中にボールを直接見るのではなく、周辺視野でボールを捉えています。そして、中心となる視野では、相手選手の身体(特に重心)や、その背後にあるスペースに焦点を合わせていることが明らかになりました。
これにより、より多くの情報を効率的に処理し、相手の次の動きを予測していたのです。
2.重心の読み方:「後出しジャンケン」で勝つ 研究は、相手の重心を観察し、それを操ることの重要性を裏付けました。三笘選手自身も「相手の重心をずらすことを意識している。相手の体を動かせたら、僕の勝ち」と語っています。相手の重心、腰、膝の微細な動きを捉えることで、相手が動いた「後」に、自分は逆の選択肢を取る。まるで「後出しジャンケン」のように、常に優位な状況を作り出すことができるのです。
3.予測的な情報収集:ボールが来る前に勝負は始まっている 優れたドリブラーは、ボールが自分に届く「前」に、すでに相手DFの位置や周囲のスペースに関する情報を収集し終えています[13]。これにより、ボールを受けた瞬間に迷うことなく、最適なプレーを即座に実行できるのです。
ドリブルの3フェーズ理論:科学的根拠の実践
三苫選手のドリブルは、これら研究で得た知見をピッチ上で実践した、一連のプロセスと見ることができます。
|
フェーズ
|
名称
|
内容
|
戦いの種類
|
|
1
|
戦術的セットアップ
|
巧みなボールの置き所と身体の向きで、相手DFの動きを止め、思考を「フリーズ」させる。
|
思考の戦い
|
|
2
|
生体力学的実行
|
相手を静止させた瞬間、「反発ステップ」などの技術で爆発的に加速し、物理的な優位を確立する。
|
物理の戦い
|
|
3
|
認知的読解
|
加速しながらも相手の身体情報を読み取り続け、最終的な突破方向を決定する。
|
情報の戦い
|
三苫選手のドリブルの凄みは、これら「思考」「物理」「情報」という3つの異なる領域の戦いを、一瞬のうちに、かつシームレスに統合・実行できる点にあります。
論文の真の価値:思考法そのものの習得
上述ましたが、三笘選手本人は、論文がメディアで「誇張されてる」と語り、現在のプレーへの直接的な影響を控えめに評価しています。しかし、この謙虚な発言こそが、論文の真の価値を物語っています。
論文執筆の本当の成果は、ドリブルの「秘訣」を記したマニュアルを手に入れたことではありません。
それは、自らのパフォーマンスを客観的に分析し、仮説を立て、データを基に検証し、言語化して体系化するという「科学的思考法」そのものを習得したことにあります。
この思考法こそが、彼の成長を支え続ける根源的な力となっているのです。
【肉体】理論を実行可能にした4年間の肉体改造──ウェイトトレーニングの軌跡

卒業論文によって「ドリブルの理論」を確立した三笘選手。しかし、どれほど優れた理論も、それをピッチ上で実行できる肉体がなければ意味を成しません。
三苫選手がプロの世界で即座に輝きを放つことができたのは、大学4年間を費やして行われた、極めて計画的な肉体改造があったからです。
大学時代の計画的肉体改造:4年間で筋肉だけを6kg増やすプロジェクト
大学進学時、三苫選手の体重は約66kgでした。プロで90分間戦い抜くにはフィジカルが不十分だと自己分析し、明確な数値目標を設定します。
それは、4年間で体重を約6kg増やし、72kgにすること。しかも、単に体重を増やすのではなく、プレーのキレを失わないよう「筋肉だけでの増量」を目指しました。
彼のウェイトトレーニングは、明確な2つのフェーズに分かれていました。
|
フェーズ
|
時期
|
目的
|
主なトレーニングメニュー
|
|
1:基礎構築期
|
大学1〜2年次
|
筋肥大と最大筋力の向上
|
スクワット、ベンチプレス、懸垂など、基本的な高強度トレーニングを週2〜3回実施。
|
|
2:応用展開期
|
大学3〜4年次
|
筋力を爆発的なスピードに変換
|
陸上の谷川聡准教授から走法指導を受け、140kgのバーベルスクワットなどでパワー向上を図る。
|
大学1、2年次でプレーの土台となる頑強な「シャーシ」を作り上げ、3、4年次でそのパワーをスピードに変換する「エンジン」のチューニングを行ったのです。
特に、陸上110mハードルの元オリンピック代表選手である谷川聡准教授に走り方の指導を仰いだ点は、彼が単にサッカーの練習をするだけでなく、より優れた「アスリート」になるために、根本的な動作様式を改善しようとしていたことを示しています。
プロ入り後の進化:身体を一つのシステムとして捉える
プロ入り後、特に世界最高峰のプレミアリーグで戦う中で、三苫選手のトレーニングはさらに洗練されていきます。単に筋肉を大きくするのではなく、身体全体を一つの連動したシステムとして捉え、その機能性を極限まで高めるアプローチです。
「フィジカルを上げれば技術もついてくる印象」
これは、プレミアリーグの激しいフィジカルコンタクトを経験した彼の言葉です。かつては身体的な不利を技術で補おうとしていた彼が、今や「強靭な肉体こそが、次のレベルの技術を解放する」という新たな境地に達したことを示しています。
三苫選手トレーニングには、体幹の安定性と身体全体の連動性を高める、ユニークなメニューが含まれています。
- 加重呼吸:仰向けになり、腹部に6kgの重りを乗せて呼吸することで、体幹のインナーマッスルを強化する。
- バランスボール・コーディネーション:バランスボールを肘と膝で挟んで転がり、身体を一つのユニットとして動かす感覚を養う。
- セット間のジョギング:彼はトレーニングのセット間にジョギングを挟みます。その目的を「使った筋肉の動きを走りに繋げたい」「脳が覚えていく」ためだと語っており、筋肉と神経の連携を常に意識していることがわかります。
肉体改造を支えたストイックな栄養管理
この肉体改造プロジェクトを陰で支えたのが、徹底した栄養管理です。三苫選手は大学時代から、栄養学に基づいた食事管理を実践していました。
そのストイックさは、専属栄養士が驚くほどです。白米の量を10g単位で調整し、苦手なセロリのような香味野菜でさえも、身体に必要だと理解すれば文句一つ言わずに食べる。
大学の寮生活時代には、自前の油や調味料を持ち込んでいたという逸話もあります。彼にとって食事は快楽ではなく、自らのパフォーマンスを最大化するための、極めて重要な「燃料」なのです。
合わせて読みたい
アスリート必見!トレーニング期と試合前で変わる食事法【トップ選手の事例付き】
・アスリートが栄養とどう向き合うべきかを解説。加えて本田圭佑、クリスティアーノ・ロナウド、大谷翔平、マリア・シャラポアの食事の考え方を紹介。
【心理学】最高のパフォーマンスを再現する──ルーティンという心理的技術
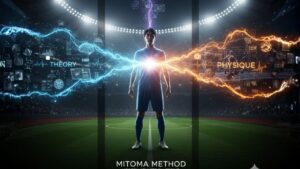
優れた理論と強靭な肉体。しかし、これらを試合本番という極度のプレッシャー下で、常に安定して発揮するためには、もう一つの重要な要素が必要です。それが、パフォーマンスを再現可能にするための「心理的技術」、すなわち「ルーティン」です。
CEO的アプローチ:「チーム三笘」とデータ主導の自己管理
三笘選手のプロフェッショナリズムは、ピッチ外の自己管理に最も強く表れています。彼は自身のコンディションを最適化するために、栄養士、パフォーマンスコーチ、トレーナーからなる専門家チーム、通称「チーム三笘」を個人的に組織しています。
これは、彼が自らのキャリアを一つの企業のように経営する「CEO」のような視点を持っていることを示しています。
そのマネジメント手法の根幹にあるのが、データに基づいたアプローチです。
所属クラブで定期的に行われる血液検査の結果を自ら要求し、その客観的なデータを分析します。そして、自身の主観的な疲労感と照らし合わせ、「これは脳の疲労か、それとも体の疲労か」を区別し、その日のトレーニング内容や食事に微調整を加えるのです。
この主観と客観の統合こそ、彼のコンディション管理の真髄です。
試合当日のルーティン:心と体を最適化する科学的儀式
彼の試合当日のルーティンは、単なるジンクスや願掛けではありません。各ステップが、心身を最高の状態にチューニングするための、科学的な目的に基づいて設計されています。
|
タイミング
|
行動
|
目的
|
科学的根拠
|
|
状態によって
|
冷たいシャワーを浴びる
|
交感神経系を活性化させ、心身の覚醒レベルを高める
|
神経系の準備
|
|
試合前
|
好きな音楽を聴く、呼吸法、イメージトレーニング
|
プレッシャーを管理し、集中を深め、成功を視覚化する
|
心理的準備
|
|
ウォーミングアップ後
|
氷嚢で身体各所(額、首筋、脇、膝裏)を冷却
|
身体と脳の「オーバーヒート」を防ぎ、鋭い集中力を維持する
|
体温・脳温の調整
|
|
ハーフタイム
|
氷嚢による冷却を繰り返す
|
後半に向けて、心身を再び最適な状態にリセットする
|
パフォーマンスの持続
|
特に、ウォーミングアップ後やハーフタイムに氷嚢で身体を冷やすという行為は、三苫選手のユニークなアプローチを象徴しています。
これは、身体と脳を、最高の処理速度を保つために常に冷却・調整が必要な精密機械のように扱っている証拠です。
他にも、コーヒーで”脳をギンギンにする”そうです。
7時にキックオフだとすると4時くらいに1回目のコーヒーを飲む。それから数回に分けてコーヒーを飲んでいくそうです。
カフェインの効果で、脳を活性化するようですね。
合わせて読みたい
【アスリート必見!!】カフェイン活用法とダイエット効果
アスリートにとって、カフェインはダイエット効果だけではなく、パフォーマンス向上と持久力向上に役立つことなどを解説。
睡眠さえも成長の糧に:能動的な回復
彼は最適な身体的回復のために、9時間の睡眠を確保することを公言しています。
しかし、彼にとって睡眠前の時間は、単なる休息ではありません。彼はその時間を、その日の試合の場面を頭の中で再生し、自身の課題に対処するためのトレーニング計画を練る、能動的な分析と計画の時間だと述べています。
「ぼうっとしている時間はあまりない」
この言葉が示すように、彼の思考は24時間、常に自己の成長に向けられています。就寝という受動的な行為でさえも、翌日のパフォーマンスを最大化するための能動的な準備作業へと変えているのです。
合わせて読みたい
用具選択の科学:スパイクはプレースタイルの延長
三苫選手の科学的アプローチは、使用する用具の選択にも及びます。彼が選ぶスパイクはPUMAの「ULTRA」シリーズですが、その選択理由は単なる好みや感覚ではありません。
その理由を「より縦の推進力を出したいタイプ」だからだと明確に述べています。
これは、三苫選手のスパイク選びが、代名詞である「反発ステップ」の生体力学や、縦への爆発的な加速力という、プレースタイルの核と直接的に結びついていることを示しています。
用具さえも、自らの理論を実践するための合理的なツールとして選択しているのです。
3つの要素の統合──「三苫メソッド」が示す現代アスリートの青写真

三笘選手の強さは、これまで見てきた「理論」「肉体」「心理」という3つの要素が、それぞれ独立して機能しているのではなく、一つの統合されたシステムとして、相互に作用しあっている点にあります。このシステムこそが、彼を継続的に成長させる原動力となっています。
成長のサイクル:PDCAを超えるOODAループ
彼の成長プロセスは、ビジネスで用いられるPDCA(Plan-Do-Check-Act)サイクルよりも、さらに迅速で柔軟なOODAループ(Observe-Orient-Decide-Act)に近いと言えるでしょう。
三苫選手のOODAループ
1.観察 (Observe):自身のパフォーマンスや身体の状態を客観的なデータ(血液検査、視線分析など)で冷静に観察する。
2.方向付け (Orient):観察で得たデータと、自身の経験や価値観、そして科学的知見を統合し、現状を正確に把握する。
3.意思決定 (Decide):課題解決のための具体的な行動計画(トレーニングメニューの変更、食事の調整など)を決定する。
4.実行 (Act):決定した計画を徹底的に実行する。
このサイクルを高速で回し続けることで、彼は常に自分自身をアップデートし続けているのです。
哲学の進化:身体は「制約」から「基盤」へ
彼のキャリアを通じて、自身の「身体」に対する哲学が進化してきたことも興味深い点です。
|
時期
|
身体への認識
|
アプローチ
|
|
幼少期〜高校
|
身体は制約
|
小柄で非力な身体を、卓越した技術で補う。
|
|
大学時代
|
身体はプロジェクト
|
理論を実行可能なレベルまで、計画的に設計・構築する対象。
|
|
プレミアリーグ
|
身体は基盤
|
さらなる技術的進化を解放するための、全ての土台。
|
この哲学の進化は、三苫薫が単なる選手ではなく、自らのキャリアをマネジメントする「研究者」であり「経営者」であることを示しています。
数値で見る成果
この統合されたアプローチがもたらした成果は、世界最高峰のリーグであるプレミアリーグの公式スタッツにも明確に表れています。
三苫選手の成績
- ドリブル成功数:1試合あたり平均2.29回(リーグ3位)[27]
- ペナルティエリア内タッチ数:1試合あたり平均6.12回(上位88パーセンタイル)[27]
これらの数値は、彼のドリブルが単なる「見せるプレー」ではなく、ゴールという結果に直結する、極めて効果的な戦術兵器であることを証明しています。
■ 指導者・保護者が学ぶべき3つの教訓
三笘選手の歩みは、育成年代の選手を指導する指導者や、子どもをサポートする保護者にとって、多くの重要な示唆を与えてくれます。
教訓1:才能は固定されていない
三笘選手自身、幼少期は小柄で身体能力に恵まれた選手ではありませんでした。三苫選手の成功は、生まれ持った才能(ハードウェア)ではなく、後天的に獲得した思考法と計画的な努力(ソフトウェア)の賜物です。
選手の成長を信じ、「才能がないから」という言葉で可能性の芽を摘まない「成長マインドセット」を持つことが、指導者には求められます。
教訓2:長期的視点の価値
18歳でプロ契約を断り、大学進学を選んだ彼の決断は、短期的な成功よりも、長期的なキャリアの成功を優先する「長期的視点」の重要性を教えてくれます。目先の勝利や評価に一喜一憂せず、数年後を見据えた育成計画を立てる勇気が、選手の将来を大きく左右します。
教訓3:科学的アプローチの実践
三苫選手の強さの根源は、「考える力」と「言語化する力」にあります。指導の現場においても、「なぜそうするのか?」を選手自身に考えさせ、自分の言葉で説明させる機会を増やすことが重要です。
感覚的な指示だけでなく、データや科学的根拠に基づいた指導を取り入れることで、選手は自己主導で成長する力を身につけることができます。
■ まとめ:「才能がない」は、選手の可能性を摘む言い訳に過ぎない
最後に、三笘選手の成功から我々が学ぶべき最も重要なエッセンスをまとめましょう。
三笘メソッドのエッセンス
三苫薫メソッド
- 理論:卒業論文に象徴されるように、「なぜそうなるのか」を科学的に探求し、言語化する。
- 肉体:理論を実行可能なレベルに引き上げるため、長期的な視点で計画的に身体を設計・構築する。
- 心理:ルーティンとデータ活用によって、最高のパフォーマンスを安定して再現するシステムを構築する。
彼の成功は、一部の天才だけが持つ特別な「才能」によるものではなく、明確な目的意識と科学的思考法に基づいた、合理的な「システム」の産物です。そして、このシステムは、どんな選手でも、どんなレベルからでも、学び、実践することが可能です。
指導者や保護者の役割は、選手に完成された答えを与えることではありません。
選手自身が「考えるアスリート」となり、自らの手で成長のサイクルを回していけるように、その環境を整え、サポートすることです。三笘薫という存在は、日本の育成年代に関わる全ての人々にとって、そのための最高の道標となるでしょう。
■ Q&A
Q1: 「うちの子には三苫選手のような才能がないのですが…」
A: その考えこそが、お子様の可能性を狭めているかもしれません。三笘選手自身、幼少期は小柄で身体能力に恵まれていませんでした。彼の強さは、生まれ持った才能ではなく、後天的に身につけた科学的思考と計画的な努力の積み重ねです。重要なのは、今の能力ではなく、成長する力そのものを育むことです。
Q2: 「卒業論文を書かないと上手くならないのですか?」
A: もちろん、そうではありません。論文執筆はあくまで手段の一つです。本質は、「なぜ今のプレーは成功したのか?」「なぜ失敗したのか?」を感覚で終わらせず、自分の言葉で説明しようと試みる「言語化の習慣」にあります。日々の練習ノートに、その日の課題や発見を書き留めることから始めるだけでも、大きな一歩です。
Q3: 「プロを目指さない子にも参考になりますか?」
A: はい、大いに参考になります。三笘選手のアプローチの本質は、「目標を設定し、現状を分析し、科学的根拠に基づいて計画を立て、実行し、改善する」という、普遍的な問題解決プロセスです。この能力は、サッカーだけでなく、学業や将来の仕事など、人生のあらゆる場面で応用できる、極めて重要なスキルと言えるでしょう。
参考文献
- 三笘薫から学ぶ「勉強 スポーツ」が最強な理由|とも(高橋知久) – note,
- サッカー日本代表・三笘薫を支える筋トレの軌跡, TARZAN
- 【2025年最新!!】三笘薫とは?経歴・プレースタイル・移籍情報・名言まとめ FootIF,
- 「なぜ、自分のドリブルは抜けるのか」意識高すぎルーキー・三笘 Number WEB.
- 三苫薫何がすごい?走り方、ドリブル、反発ステップ解説! – マタドールジム.
- 三笘薫の卒論は「極めて稀なケース」 筑波大恩師に訊く”ドリブル – Football ZONE
- 三笘薫 「ドリブルの卒論は誇張されてる」と訴える – Qoly,
- サッカー三笘薫の走りをマラソン高橋尚子が徹底分析!ミッドフット走法が共通点「S 1」
- Why did Kaoru Mitoma become strong at the “turning point” 【Interview】 – YouTube,
- 《独占インタビュー》三笘薫26歳が明かす”トレーニングの中身”がすごかった!24時間サッカー漬け「データマニアと言われたら、そうかも・・・」 - Number WB
- 【有料級】三笘薫の元トレーナーが教える1日3分でキレが激変するサッカーに必要な体幹トレーニング! – YouTube,
- 三笘薫は「食」にもストイック? ベルギー生活を支える専属栄養士が驚く“細かい質問”…「苦手なセロリもきちんと食べる、白米は10g単位で」 – Number Web,
- 【報ステ】三笘が実演解説!日本最強ドリブルの極意「インステップ」と「置き所」-YouTube,
- 「ぬるぬる感」の秘密まで徹底解剖。footballhack流、三笘薫ドリブル総論 – フットボリスタ,
- 「そう見えても仕方ないですけど…」耳に届く世間の声 三笘薫のドリブルが目立たなくなった理由【インタビュー】 | フットボールゾーン – FOOTBALL ZONE
- サッカー指導者必見!日本代表の守田や三笘の恩師たちが語った「2人は学生時代、何がすごかったのか -アットエス
- 「世界で三笘だけ」筑波大の恩師が明かす“1mmアシスト”三笘薫…陸上関係者を仰天させた話「彼を天才だと言う人もいますが…」 – サッカー日本代表 – Number Web,
- トップアスリートのパフォーマンス向上の秘訣~プラントベース食の可能性 - 筑波乳業,
- 三苫薫選手のリラックスするルーティンとは? – メンタルコーチ 西田明,
- 「(三笘)薫は冷たいシャワーを浴びている」日本代表・守田英正が語る“試合当日のルーティン”「カフェインで脳をギンギンにする」(3 – Number Web,
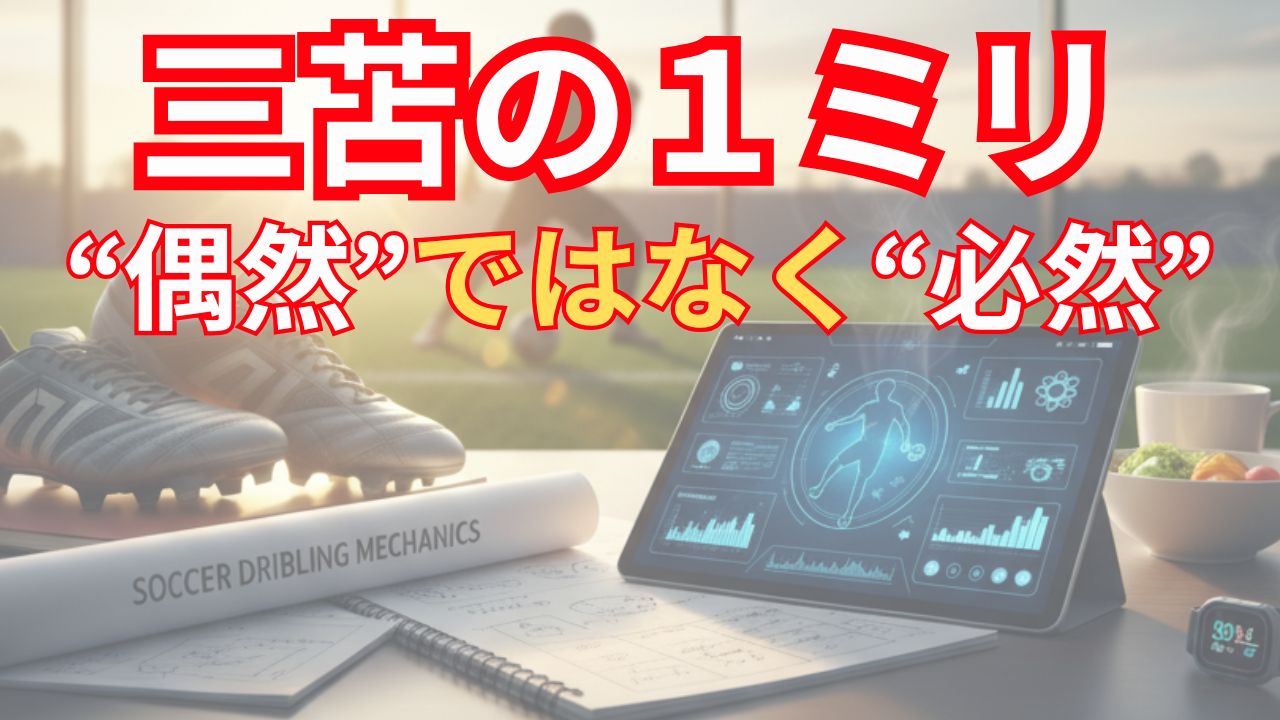
コメント